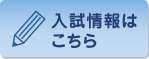8月9日、地学部は神奈川県三浦市の城ケ島に巡検に行きました。島は海食台でできており、大変きれいな地層が露出しています。断層や褶曲のほか様々な地質構造が見られ「日本の地質百選」にも選ばれている場所です。猛暑日で過酷な環境ではありましたが、風光明媚な城ケ島の成り立ちや地史に思いをはせながら、汗を滴らせて地層の走向と傾斜を測ってきました。

海食洞門である「馬の背洞門」の前で集合写真。大正関東地震で土地が隆起する前は、小舟が通過できたそうです

亀の子島のコンボリュートラミナ。未固結の堆積物から急激に脱水が起こったことを示しており、脱水が上方へ起こることから、地層の上下判定に使うことができます。この地層は上下が逆転しています

赤羽根海岸。ウミウの生息地として有名です。関東ローム層が露出しています

こちらの断層では、油壺層と初声層が接しています

このように、城ケ島ではいくつもの小断層を観察できます

クリノメーターを使ってたくさんの走向・傾斜をはかりました

白い凝灰岩層に見られる火炎構造。炎がゆらめいているような断面をしています。未固結の堆積物の上に砂層が堆積し、その荷重で砂が下に沈み込んでできたものです
 地学部 城ケ島巡検
地学部 城ケ島巡検